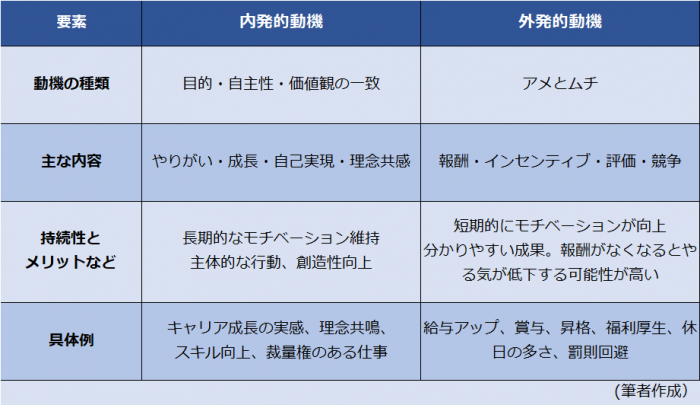現場トラブルの真因を断つ── 中小企業における構造的マネジメントの再構築
現場トラブルの真因を断つ──
中小企業における構造的マネジメントの再構築
■先週も月曜日から土曜日まで仕事でしたが、
日曜日は家族3人で目白台の椿山荘に桜を見に
行ってきました。
椿山荘は、明治時代の元勲・山縣有朋が築いた
場所で、彼の趣味である庭園づくりが反映され
ています。
敷地内には美しく整えられた樹木や噴水などが
あり、歩きながら景色を楽しめるようになって
います。
当日は、のんびりとした時間の中で、庭園や
満開の桜、そして広がる空を眺めながら、
心が洗われるような穏やかなひとときを過ごし
ました。

■最近のご相談事例より
現場では、日々さまざまなトラブルが発生して
います。
たとえば、思うように成果が出ない、
社員の退職が相次ぐ、
顧客からのクレームが続く
──このような問題が一切ない職場は、
ほとんどありません。
こうした現場で奮闘しているのが、
いわゆる「プレイングマネジャー」と呼ばれる
管理者たちです。
彼らは、自分自身も実務をこなしながら、
同時にチームのマネジメントも担っています。
しかし実際には、チーム運営やメンバー育成に
十分な時間が取れず、多くの時間をプレイヤー
業務に費やしているのが現状です。
■加えて、日々の突発対応、成果へのプレッシャー、
残業削減、コンプライアンス対応、価値観が多様
な部下との関わりなど、管理者には多方面からの
負担が重くのしかかっています。
そして、そのような管理者の姿を見た若手社員
からは、
「自分は管理職になりたくない」
「管理者って大変そう」
といった声もあがり、次世代の管理職を育てる
うえでの課題にもなっています。
■このような会社では、同じような問題が何度も
繰り返し発生し、そのたびに対処する
──まるで「モグラ叩き」をしているような
状態が続いているケースがよく見られます。
こうした状況の問題は、特定の社員さんや
マネジャーの意欲や能力が足りないことでは
ありません。
その真因は、そうした状況を生み出している
会社の組織の仕組みや運営のやり方にあります。
そこに目を向けることで、モグラ叩きのような
対処療法から抜け出し、根本的な解決への道が
見えてくるのです。
■私たち中小企業において、現場で発生する
さまざまな課題への対応策の一つとして有効
な手段が、ミドルマネジメント機能の強化と
発揮です。
「ミドルマネジメント」とは、
企業によって呼称に差はありますが、
一般的には課長、部長、営業所長、
チームリーダー等の中間管理職を指します。
この層は本来、経営方針と現場実務の橋渡しを
担う、極めて重要な役割です。
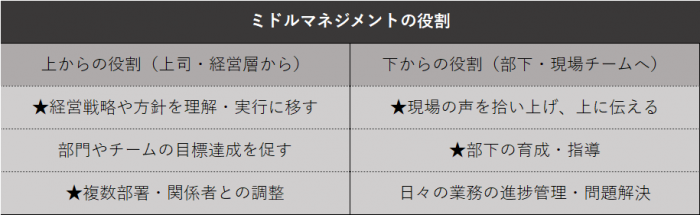
(筆者作成)
■本来であれば、こうしたミドル層が、部下の育成、
チーム運営、業務推進、現場との調整などを担う
べきですが、中小企業においてはさまざまな制約も
あり、日々の実務に忙殺され、十分に機能しづらい
状況にあるのが現実です。
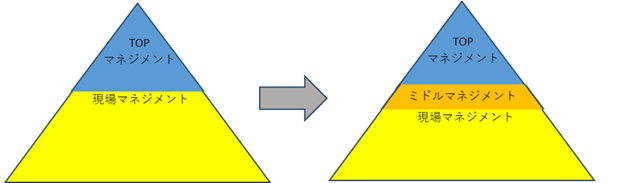
(筆者作成)
■そのため、私たち中小企業においては、
TOPマネジメントがミドルマネジメントの
役割の一部を代行することが現実的な処方箋と
なります。
ただし、その際には、すべての役割を担おうと
するのではなく、上記、ミドルマネジメントの
役割表の★印をつけた箇所に主に取り組みます。
また、TOPマネジメントがミドルの役割を担う
際には、以下の点に留意することが求められます。
・一方的な指示命令に偏らないこと
・現場との認識のズレ(温度差)に配慮すること
・自ら業務を抱え込みすぎず、適切に委譲・分担すること
これらを踏まえたうえで、ミドルマネジメントの
機能を意識的に補完していくことで、モグラ叩き
のような対処療法から抜け出し、根本的な解決へ
の道が見えてくるのです。
以上、最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今日も、皆さまにとって、
最幸の一日になりますように。
日々是新 春木清隆
―――――――――――――――――――――
「強いチームは、強い中間層に支えられている。」
作者不詳
―――――――――――――――――――――