役職者の第2領域
役職者の第2領域
■先週は、1日に2件~3件稼働の日が
3日間あり、密度の濃い週となりました。
新たなマネジメントチームの組成(活性化)、
経営諸課題の解決、継続している人財育成など
の内容でしたが、各社ともに積極的な取り組み
姿勢で、期待以上の成果が体感できたのでは
ないかと感じています。
タフな週でしたが、頑健な身体に産んで、
育ててくれた両親に心から感謝です。

(今朝の空 出張先の宿から)
■ご相談の現場で、よく出てくる課題に生産性の
向上があります。
会社によって、背景は異なるものの、生産性が
伸び悩んでいる会社に共通している要因として
役職者の仕事の<質>が、期待し、要求されて
いるレベルに達していないことがあります。
そして、何故それが出来ていないのか、
現状を確認すると、これまた共通して
「人手不足」や「忙しい」という答えで
ドヨ~ンとした重い空気がただよいます。
■一方、着実に生産性を上げ続けている会社も
一定数あることも確かな事実です。
以下の図は、顧問先の会社で役職者向けに
継続して行っている勉強会資料で、2019年に
実施した内容の一部です。
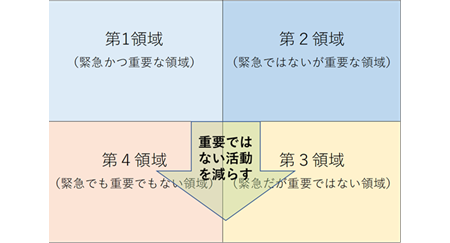
第2領域については、ご存知の方も多いと思います。
しかし、「知っていること」と「できること」には
大きな違いがあり、「できないまま」になっている
会社が少なくないのではないでしょうか。
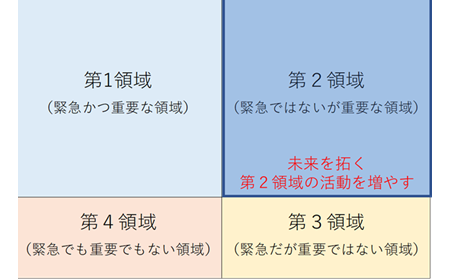
■下の図表は、同じ役職者勉強会で、第2領域に
関する情報を現場の視点から表現したものです。
現状、役職者はプレイヤー業務も担っています。
そのプレイヤー業務に忙殺され、本来の役職者の
業務がなされていない現状です。
結果、役職者はじめメンバーも疲弊し、生産性も
上がりません。
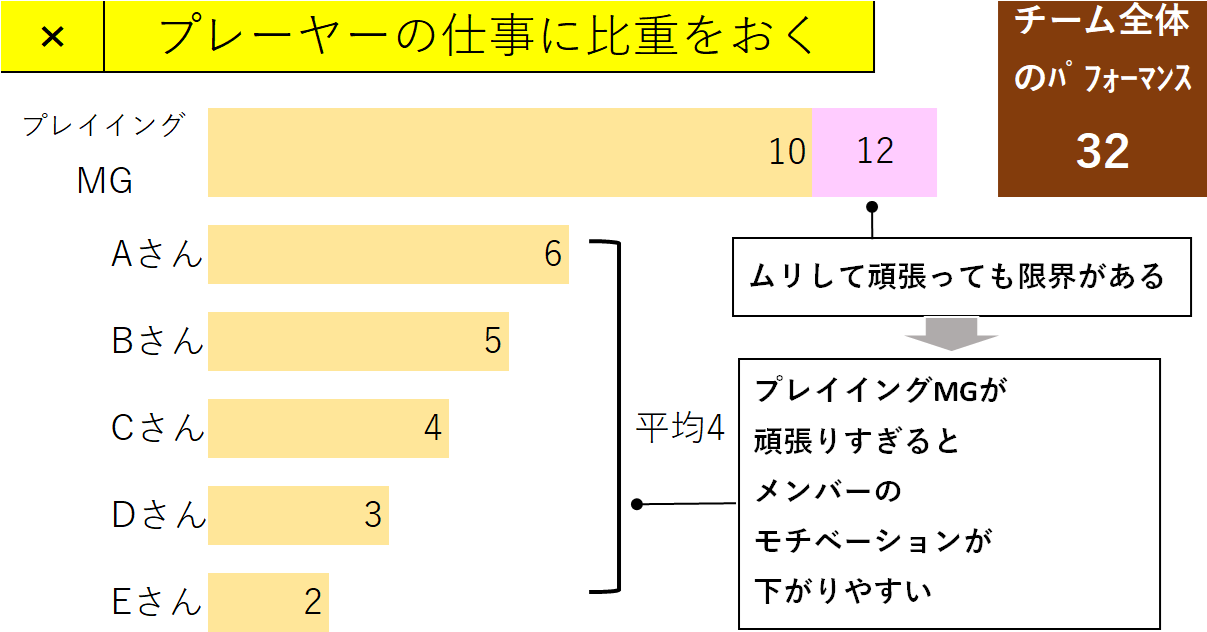
そこで、役職者が本来の業務に取り組むべく、
プレイヤーの仕事を減らし、メンバーの育成や
チーム全体の生産性向上に取り組むことで、
全体のパフォーマンスは32から36の13%増を
目指すというものです。
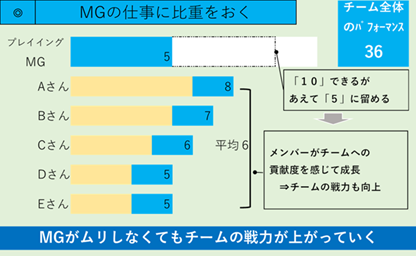
■この会社の場合、勉強会を起点に、役員はじめ
上級役職者が一丸となって、役職者の第2領域に
あてる時間を増やす取り組みを、現在も継続して
います。
その途中経過は、2018年時点で、役職者の就業
時間内の25%が第2領域だったものが、
2023年には30%と5ポイント上昇しています。
そして、上昇分の5ポイントをどのような時間に
充てているかというと、メンバーの育成と、
コミュニケーションが主な内容でした。
5ポイントが、多いのか少ないか、の評価は別と
して、この会社ではコロナ禍中も増収増益を続け
昨年度年商100億円を突破しています。
■その根底にあるのは、
<知っていること>
↓
<やること>
↓
<やり続けること>
という、当たり前のことを当たり前に行う
至極単純ですが、根気のいる作業をやり続ける、
<何としてでも>の強い意思だとかんじています。
以上、最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今日も、皆さまにとって、
最幸の一日になりますように。
日々是新 春木清隆
――――――――――――――――――――
「継続は力なり」
住岡夜晃(宗教家 1895~1949年)
――――――――――――――――――――
